実験論文では、研究者が構成した人工的環境下で人間の行動を観測し、因果関係に関する仮説を検討した活動報告をするもので、その構成は、一般に、序論、方法、結果、考察の四部からなるとされます。
そこで、それらの章立てにおいて記すべき項目を、
この記事ではさらっと
本当にさらっと示しておきます。
序論 〜仮説を記す〜
第一に、序論は仮説を導く過程です。
実験研究では、仮説がもっとも重要であるとされます。
なぜなら、仮説が明確でないと、実験において何を操作し、何を測定しようとしているかがわからないからです。
そのため、この序論において、従属変数としてどのような結果を測定し、そこに影響を与える原因としてどのような独立変数の操作を行うのかを明確にする必要があります。
ただし、適切な仮説を設定するためには、念入りな先行研究のレビューを行わなければならず、研究で取り扱おうとしているテーマが、過去の研究でどのように扱われてきたのかを理解しなければ、意義のある研究とはならないからです。
実験デザイン
仮説を示したら、序論の最後に実験デザインを組み込みましょう。
実験研究では、2群以上の比較が行われることが一般的ですが、その際にどのような群に被験者を割り当て、どのようにその結果を測定するかを記述することで全体の概観および、独立変数の要因や水準間の違いを示し、従属変数を明確にしなくてはなりません。
方法 〜各種リソースとその手続き〜
第二に、方法論について述べましょう。
この章ではその名称の通り、実験を行うために必要とされたリソースやその導入方法などについて記述します。
例えば、そこには被験者についての情報も含まれるため、ここで被験者の人数、条件、属性、など、「100名の男女学生がA群とB群にランダムに割り当てれられた」のような情報を明示します。
また、実験に使用した器具や実際にはどのような手続きで実験が進めらたかを具体的に示すことも求められます。
特に、実験研究では、変数統制のため、ディセプションを用いることが避けられないこともあり、その際は、ディブリーフィングの項目でその旨を記述しておかねばなりません。
加えて、どの研究にせよ、被験者に対して、研究目的や概要を示し、参加の同意を求めるインフォームドコンセントを得る必要があるので、その取得については、この方法の項目で明確にしておきましょう。
結果 〜分析方法とその理由〜
第三に、結果の記述です。
この章では、得られたデータについての統計的分析結果を述べます。
実験研究の分析方法としては、t検定や分散分析を用いられることが多いですが、なぜその分析を行なっているかを明確にします。
考察 〜解釈は唯一のものではない〜
最後に、考察の記述ですね。ここが初学者にしてみれば最難関かもしれませんが、あれこれ解釈をつけることこそ研究の醍醐味だとも言えます。
この章では、仮説を軸に結果の解釈を試みます。
まず、仮説に対して、それを支持する結果が得られたかどうかを明確にし、証明されなかった場合は、その理由を検討し、研究の限界についても述べます。
また、結果を解釈する際には、一般的な言及に留まらず、他の解釈可能性にも言及することで、視野の広い公平な姿勢を示すことも重要です。
そのような客観的な姿勢こそが、次なる研究の仮説を生み出すという点で価値があるからですね。
より、具体的な書き方が知りたい方へ
研究デザインにもよるかと思いますが、実際の実験を想定した記述について知りたい方は以下をご参考ください。
↓↓t検定を想定する場合
↓↓分散分析を想定する場合

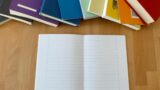



コメント