この記事は、臨床心理士資格試験の1次試験の対策ページです。
今回は「認知バイアス」に関する問題について取り上げています。
出題のポイント
「認知バイアス」に関する問題は、臨床心理士資格試験においては、どのように出題されるのでしょうか?
過去問の傾向を見ると、以下のポイントはおさえておきたいところです。
- 帰納的推論と演繹的推論の定義
- 利用可能性ヒューリスティックとその具体例
- 確証バイアスとその具体例
- 正常性バイアスとその具体例
- 後知恵バイアスとその具体例
- 内集団バイアスとその具体例
問題①~帰納的推論と演繹的推論~
ある主張や仮説が正しいことを前提に、そこから論理的に正しい結論を導き出す推論のことを「帰納的推論」と呼び、観察した事実や事象に基づいて原因や法則性を導き出す推論のことを「演繹的推論」と呼ぶ。
問題②~利用可能性ヒューリスティックとその具体例~
3文字目にkがつく単語よりも、1文字目にkがつく単語の方が多いと感じるのは、「利用可能性ヒューリスティック」の1例だと言える。
問題③~確証バイアスとその具体例~
地震速報が発令されても人々が避難しようとしないのは、「確証バイアス」の1例だと言える。
問題④~正常性バイアスとその具体例~
正夢を見たと思うのは、「正常性バイアス」によるものである。
問題⑤~後知恵バイアスとその具体例
あるYouTuberがテレビに露出するようになって、「はじめからそうなるとおもっていた」と考えるのは「後知恵バイアス」である。
問題⑥~内集団バイアスとその具体例~
自分のクラスの方が、他のクラスよりも素行が良いと思うのは、「内集団バイアス」である。
答えと解説
答えと解説が知りたい方は↓こちら(=゚ω゚)ノ



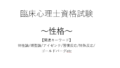
コメント